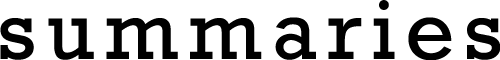こういう経験は割と誰にでもあるんじゃないかな。人は時間の長さを感覚的にしか捉えられない。だからこういうギャップが起きるのだろう。
僕は当時、東京で学生をしていた。後にも先にも、自分自身についてあれ程考えた時間はないと思う。そういう時間の中を、ある女の子と過ごした。筆で描いたように美しい黒髪と切れ長の目をした女の子だった。
僕と彼女は恋人ではなかった。かと言って友人でもない。そういう奇妙な関係を保ちながら、しばらくの間同じ部屋で暮らしていた。その経緯を全て伝えるとあまりに長くなるので、僕達が初めて言葉を交した時の事を少しばかり話そうと思う。
それは7月の夏だった。クーラーのよくきいた部屋の外で、蝉達の命を振り絞る声が微かに聞こえる中、僕はラテンアメリカ文学の講義を受けていた。確かフリオ・コルタサルの短編『山椒魚』についての話だったと思う。彼女は突然に僕の隣へ座り、小声で「君、都築君だよね」と話しかけてきた。
「そうだよ、君は確か竹内の」と僕が言ったところで、彼女は遮るように「もう終わっている」と言いながら笑みを見せた。
彼女は僕の数少ない友人、竹内の恋人だった。今までキャンパス内で何度か並んで歩く姿を目にしたことがあったけれど、本当に絵になる二人で、2000年代の恋愛ドラマを見ているようだった。しかしそんな彼女がどうして僕に声をかけるのか、さっぱり見当がつかなかった。
「ところでこれは一体何用ですか?」
僕がそう聞くと、彼女は「あなた、誰に対してもそういう言葉使うの?」と聞いてきた。
「そうだよ、で、何用」
僕がそう言うと、彼女は乾いた笑いを吐きながら言った。
「悪いんだけど、少しの間君の家に泊めさせてもらえないかな?」
「そりゃ、どうして?」
「ちょっと身内でややこしいトラブルが起きたの。それについては触れないでほしい。今は漫喫とかカプセルホテルで暮らしてるんだけど、お金がなくなっちゃいそうなの。だから泊めてくれる人を探し始めた訳なんだけど、私ってこういう性格だし、そういうこと頼める女の子の友達なんてまずいないの。でも、男友達の家にお邪魔して男女の友情に亀裂が走るのも嫌なんだ。で、その諸々を竹内君に話したら、ぴったりな奴がいるって聞いて、あなたを紹介してくれたの。弱みを握ってるから断れるわけないって」
あぁなるほど、と僕は思い、そして竹内に呆れた。
「事情は分かった。教授が睨んでるから、ちょっと外で話そう」
僕がそう言うと、「睨ませておくくらいが丁度いいのよ」と意味の分からない返答が返って来たので、僕が先に席を立った。
それから、数分後には3万円を家賃と生活費としてもらう事で合意し、彼女は僕の古いけれどやたら広い方南町駅のアパートへ大量の荷物と共にやってきた。部屋に入って早々、彼女は僕のソファに座り、マルボロメンソールを吹かしながら「ほんと呆れるくらいぼろい部屋だね」と言った。
はっきり言って、彼女の暮らしぶりは“ひどい”の一言だった。
当然、家事と名のつくものは一切やらないし、ゴミも服も散らかしたままだった。夜の10時ごろに部屋を出たかと思えば、翌日の昼過ぎに酒の香りを纏って帰宅し、死んだように眠る。そんな日が週に3回はあった。酔いつぶれた彼女を新宿へ迎えにいくことなんてざらだったし、中にはケンタウルスのような逞しい体つきのアメフト男子が彼女を求めて玄関のドアにタックルしてくるなんて事もあった。
美人というのは物語のある人生を生きる定めなのだろうか。
そんな彼女が、毎月25日だけは両手にスーパーのレジ袋を提げて帰って来た。初めて見た時は目を疑ったが、彼女は笑みを見せてこう言った。
「毎月25日は餃子の日なの」
「そんな話きいたことがないけどな」
「そりゃそうだよ、私の家の習慣だもの」
彼女は髪を結わえてキッチンに立つと、慣れた手つきで野菜を刻み、調味料と具材を混ぜていった。僕はその後姿をソファに座りながら眺め、つくづく絵になる人だな、と思った。
「ほんとに料理できるんだね」
僕がそう言うと、「餃子だけだよ。それ以外の料理はほとんど作った事がない。おばあちゃんがこれだけは覚えろってよく言ってたの」
「花嫁修業に餃子の作り方とは、何ともユニークな家庭だ」
「うち、親がアホみたいにぽんぽん子供作ったおかげで、ほんと貧乏な家庭になっちゃったの。それにお母さん私が中二の時に他の男と消えちゃうし。残された私達はそれなりに苦しい思いをして生きてる。でも、毎月25日、お父さんとお兄ちゃんの給料日だけはほんのちょっとの贅沢で、お婆ちゃんが餃子を山のように作ったの。本当に山のように。だから半強制的に手伝う事になってたわけ」
「それがこの餃子と」
「そう。お婆ちゃんはもう死んじゃってるから、作り方を完璧に知ってるのは私だけ。これぞほんとの無形文化遺産だよね。レシピを残すことに何の意味があるのかなんて言わないでね。君平気でそう言う事言いそうだから。私だって意味なんて分かってないし。でも残すの、そして私が死んだ時、また誰かに引き継ぐの」
僕と彼女は皮で餡を包みながらそんなやり取りをした。
それは間違いなく、僕が今まで食べた中で最高の餃子だった。話を聞いたこともあってか、なんだか凄く深みのある味がした。
僕のシャツを着た彼女は、金麦の350ミリ缶を開け、喉を鳴らしながら勢いよく飲むと、餃子を口へ運び、そしてこう言った。
「こういうのも何だけどさ、あなたとこの餃子を食べられて良かったと思ってる。今まで色んな男の人と食べてきたけれど、あなたと食べるのが一番美味しい」
彼女はうっすらと笑みを見せながらそう言った。
僕は、その時間がこれからもずっと続けばいいなと思った。ずっとずっと、死ぬまで続けばいいなと。そして彼女の事をいつの間にか好きになっている自分に気がづいた。でもその気持ちについて話すことは一度もなかった。彼女が僕に求めるものは、そ…